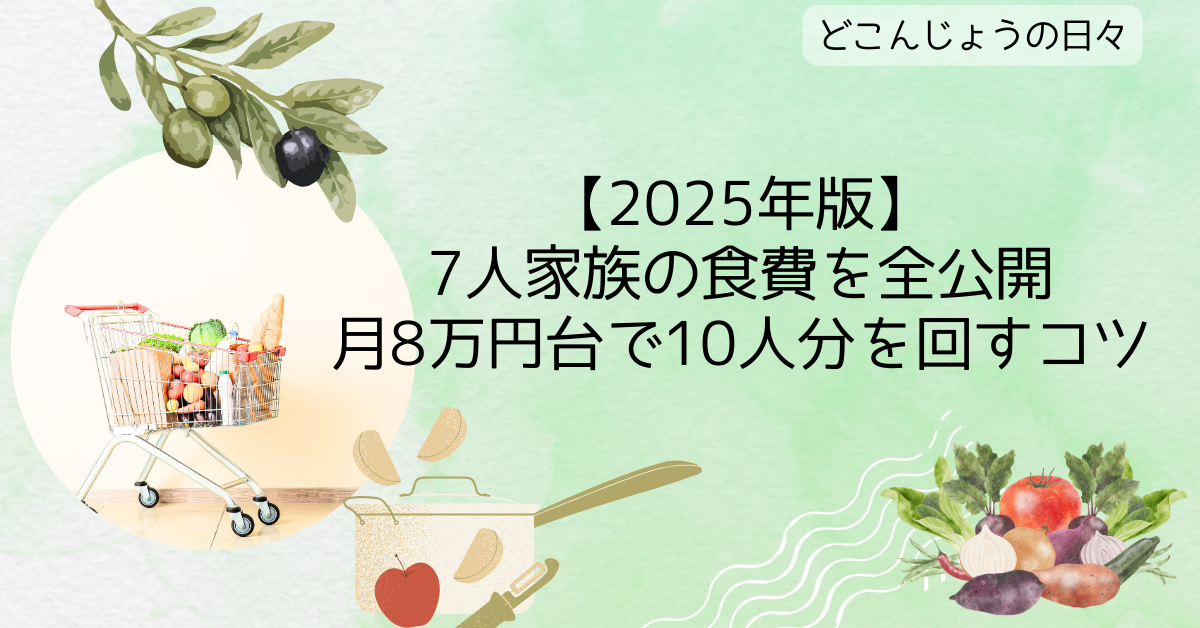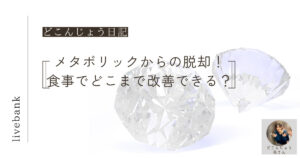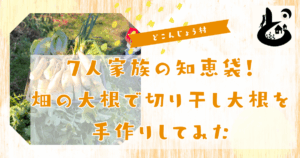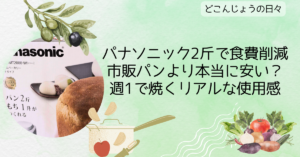こんにちは。
7人家族でステップファミリー、シェアハウスを運営中。
どこんじょう村を作りたい! どこんじょう母さん(@soratobunezumin)です。
2025年現在、育ち盛りの5人の子ども(高校生2人、小学生2人、保育園1人)と大人2人+住民3人。
そんな我が家の食費について紹介していきたいと思います(*´∀`*)
現在までの食費の推移
野菜の高騰化や流通による変動など(鳥インフルエンザとか)家計を圧迫しがちな食費。
特に7人家族の場合、月10万以下で抑えるのはなかなか難しいところ。
0〜60代という幅広い世代がいる10人(家族7人+住民3人)でどうやってやりくりしてきたのか、具体的な食費節約術を紹介していきます。
我が家の食費推移(2021〜2025年)
| 月 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 72,288 | 57,546 | 43,071 | – | – |
| 2月 | 101,752 | 63,594 | 52,579 | – | – |
| 3月 | 72,736 | 80,930 | 78,723 | – | – |
| 4月 | 105,426 | 48,759 | 49,817 | – | – |
| 5月 | 78,968 | 74,450 | 85,499 | – | – |
| 6月 | 115,845 | 67,995 | 134,658 | – | – |
| 7月 | 101,605 | 66,171 | 72,141 | – | – |
| 8月 | 68,228 | 53,572 | 77,162 | – | – |
| 9月 | 103,537 | 63,955 | 86,257 | – | – |
| 10月 | 82,843 | 47,896 | 92,717 | – | – |
| 11月 | 66,211 | 66,476 | 70,145 | – | – |
| 12月 | 70,203 | 61,902 | 110,566 | – | – |
| 平均 | 86,637 | 62,770 | 79,445 | – | 83,980 |
2025年の食費:月平均¥83,980
ちなみに買い物の頻度は変わっておらず、基本的には1週間に1回程度食材をまとめて買っています。
平均の消費とエンゲル係数
さて、7人家族の食費についてですが、いつも参考にしている羽仁もと子式でいうと、我が家の目安は13万!らしいです。
その一方で、You Tubeなどで人気のご家庭では9人家族で食費6万円など、この辺かなり格差があるなぁと感じています。
 どこんじょう母さん
どこんじょう母さんただただスゴい。
我が家の食費は1ヶ月に換算すると¥83,980。
6人以上の家族の理想的な食費は、エンゲル係数(所得に対する食費の割合)を基に計算できます。計算式は以下の通り。
**消費支出(円)×エンゲル係数(%)=食費の目安(円)
6人以上の家族の場合、消費支出の平均が36万円で、エンゲル係数は29.8です。これを計算すると以下の通りになります。
360,000(円)×29.8(%)=107,280円
計算上は10万7,000円ほどが、7人家族の1ヶ月分の食費として最適解となります。
引用元:7人家族の食費の平均はいくら? 世帯人数や年収別に食費を比較
- 食費:¥83,980
- 消費支出:¥248,661(光熱費・消耗品除く)
- エンゲル係数:33.8%
ちなみに6人家族の目安が約30%くらいなので、7人家族で考えると少し高めですが、10人分なので許容範囲かなと。
2025年の食費内訳
2025年の食費内訳はこんな感じです。
| 項目 | 月平均 | 備考 |
|---|---|---|
| 副食物費(肉・魚・野菜等) | ¥45,410 | – |
| 主食費(米・パン・麺等) | ¥30,742 | 外食費を含む |
| 調味料費 | ¥7,828 | – |
| 合計 | ¥83,980 | 10人分 |
- 副食物費:¥45,410
-
- 魚介類:¥2,457
- 肉類:¥10,345
- 卵:¥2,772
- 牛乳・乳製品:¥2,447
- 野菜・海藻:¥4,910
- いも類:¥155
- 青果類:¥427
- 豆・種実類:¥1,878
- 果物類:¥482
- お菓子類:¥5,656
- その他:¥13,881
- 主食費:¥30,742
-
- 米類:¥12,290
- パン類:¥2,496
- 麺類:¥1,683
- 粉類:¥54
- 乳児用:¥367
- 外食:¥13,735
- その他:¥117
- 調味料費:¥7,828
-
- 味噌・醤油・塩・酢:¥226
- 砂糖類:¥214
- 油脂類:¥468
- バター類:¥16
- 他の調味料:¥1,737
- 茶・コーヒー:¥296
- 飲料・嗜好品:¥4,735
- その他:¥136
悩みと課題
食費はどこまでが必要なのか?って各家庭の健康状態や生活状況によるのでまちまちだと思うんですが、うちの場合は上記のような内訳です。



長男・次男が高校生になり、食べる量が完全に大人を超えてきた!
ご飯の消費がえげつない。
5合炊いても足りないこともあります。
「腹減った〜」と言いながら冷蔵庫を開ける音が恐怖(笑)
しかも2人とも通信制高校なので、朝昼は家でご飯を食べてます。
1日3食×2人分が毎日追加されるので、食費が上がる上がる…
とはいえ、昼は自分たちでチャーハンとか納豆ご飯とか米メインで簡単に食べてるみたい。
手のかかるおかずは作らないので、その分は助かってます。
とりあえず米さえ炊いておけば、あとは各々でなんとかしてくれる。
三男(小学生)も兄たちに負けじと食べ始めてるので、男の子3人の食費がこれからどこまで上がるのか・・・
密かに焦っています。
一方で、長女(小学生)と次女(保育園)は女の子なので、まだ食べる量は控えめ。
でも次女がどんどん離乳食から普通食に移行してきて、めきめき食べるようになってきました。
赤ちゃんの頃はミルク代が1ヶ月10,000円くらいはかかってたので、それがなくなったのは助かりました。
でも、保育園に行き始めて食欲旺盛になってきて嬉しい半面恐怖ですね(笑)





給食ももりもりお代わりしているらしい。
食費節約の基本的な考え方
食費の予算設定方法
いちばん大事なことは、予算の設定です。
家族の人数や子供の年齢によって変わるので一概には言えませんが、ライフスタイルに合った予算を立てることでコントロールしやすくなります。
もちろん、ライフスタイルが変わったら予算も変わるのでその都度見直します。
家計簿のススメ
現状の把握にはやはり家計簿!
面倒でも品目ごとに記録して、集計します。
特に膨らみやすい食費。
過剰になっている場合は見直しのタイミングです。
逆に食費が不足している場合は、無理せず工夫をして予算を管理する必要があります。



食事を切り詰めて病気になったら元も子もないからね!
具体的な食費節約術
買い物のコツと節約食材
食料品は、買いすぎると使いきれず冷蔵庫の奥でひっそり萎びていたりカビていたりしますよね。
なので、冷蔵庫が空になってから買い物に行きます。
まとめ買いの頻度としては、1週間に1回買って使い切ったら買いに行くスタイル。
特売品には飛びつかず、欲しい物が安くなっていた場合のみ買います。



特売品でも元が高いこともあるから気をつけてね!
例えば、コストコで肉を買う場合もグラムを見て購入。
スーパーより高いものは買いません。
狙い目は、豚のブロックやひき肉、鶏肉です!
豚ブロックは切る手間はあるけど、スーパーで買うより安い時もある。


冷蔵庫だけでは足りないので冷凍庫を追加してやりくりしてます。
自炊のメリット
食材だけでなく調味料もアレコレ買ったりしません。
これは冷蔵庫をスッキリさせるのと使い残しを防ぐのもあるんですが、便利な調味料って日々たくさんでてますよね。
チューブのものとかドレッシングとか、買って数回しか使わず賞味期限切れてる・・・っていうのはよくある話(実家あるある
それが嫌なので、調味料は最低限にして、冷蔵庫やストック場所に入る量しか買いません。
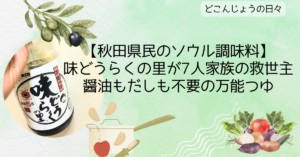
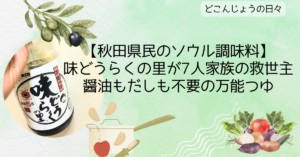
昼食は節約重視
夫と私は外で仕事をする時はお弁当持参にしてなるべく昼は節約しています。
コンビニや外食だと1食¥500〜800かかるけど、お弁当なら¥200〜300で済む。
2人分だと月¥12,000〜18,000くらいの節約になります。
一方で、大家族では家族全員での外食はほとんどしないと思いますが、月1回など限度を決めて、家族での楽しみとしています。


これもなくそうと思えばなくせるんですけど、家族ででかけてお店で食べる特別感ってワクワクしますよね(私だけ?
子どもが大きくなるとそもそも一緒に外出もできなくなってくるだろうし。
そこは「お楽しみ費」として確保してもいいんじゃないかなーと思います。
家族で外出した際のご飯について、手作りのお弁当を作ってのお出かけは一番お金もかからないと思うんですが・・・
私はストレスがかかるのでやめました(笑
食事の準備と管理
そもそも食材を無駄にしないことですね。
そのために冷蔵庫の中身の把握をしやすい配置にしたりして無駄な買い物を減らします。
野菜は八百屋さんで買ったり、旬のものを選ぶなどして節約に繋げます。
食事を管理することで、結果的に、夫がメタボリックから脱却できたりと副産物もありました。
節約生活をしてみてのアドバイス
そんなわけで、5年間記録を取ってみた経験からのアドバイスをいくつかお伝えしたいと思います。
節約術を実践した結果
食費を節約するぞ!と意気込んで、10人家族になったりしても月の食費を10万円以下に抑えられるようになりました。
1人あたりの食費を平均して計算すると、1ヶ月で約¥8,398。
10人で月¥83,980、1人1日あたり¥280。
外食含めてこの金額なら、頑張ってる方かなと。
ここまで書いてきたように、節約術と言ってもなにか新しいことをするわけではなく「よく聞く節約のコツ」はやっぱり理にかなっているな。というところに落ち着きました。
2023年は妊婦だったのでOisixに頼ったこともありますが、そもそも大家族向きでないことと金額が高くつくので、3ヶ月ほどお世話になって止めました。



世帯人数が少ない家庭は、便利かも。
節約生活のコツ
やはり、まとめ買いが重要です。



ただし、いつも買わないけど安売りしているものには飛びつかないように。
そして、食材は冷凍などをしてストックしておくこと。
それを冷蔵庫は1週間、冷凍庫は1ヶ月で使い切るのがポイントです。
作り置きは、大家族ではあっという間に食べてしまうので都度作ったほうが無駄がありません。
残ったものは翌日の朝食やお弁当などにして食べきりましょう。
まとめ
主食やメイン、副菜を切り詰めると、栄養素が足りず体のバランスが崩れるということがあります。
一方で、つい手に取ってしまう嗜好食品は「お楽しみ」的な要素が多いので、ぶっちゃけなくてもいいわけです。
でも、甘いものってやっぱり美味しく感じるし、みんなでわいわい食べると楽しい思い出になる。
誰かが遊びに来たり、お出かけしたり、あるいは誕生日には解禁するとか、メリハリをつけてあげると結果的に余分な食費が節約できるのです。


カリカリ節約するだけでなく緩めるところを作りながら、心の余裕を持つ。
上手に工夫して食費の節約できたら最高ですね。
同じく大家族で食費に悩んでる方、一緒にやりくり頑張りましょう!